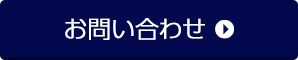先日、政府よりブラック企業の法令整備と取り締まり強化のニュースが発表されました。
・政府「ブラック企業」取り締まり強化と労働規制緩和の環境整備を検討
・ブラック企業撲滅に向け議論開始へ 政府
そこで、ブラック企業と長年向き合ってきた誹謗中傷対策センター(ネクストリンク株式会社)の目線から
ブラック企業の現代(いま)をお伝え致します。(全3回)

←前回を振り返る:ブラック企業と現代 <前編>/独り歩きする言葉
(文・ネクストリンク株式会社 代表取締役社長 大和田 渉)
弊社が取材などお受けする際に、多く受ける質問が、
「ブラック企業問題とブラック企業の定義について」です。
質問の回答として必ずお話しするポイントとしては、
「違法性の有無」と「労働と報酬のバランス」のお話をさせて頂いています。
まず、「違法性の有無」に関しては、
『一生懸命頑張っている会社』と
『違法性のある会社や反社会的な勢力との関係を持つ会社』が
少々混同されてしまっている節があります。
法令の範囲内であれば、労働時間が長い、業務負荷が高いというだけではブラック企業とは呼ぶべきではないと考えます。
次に、「労働と報酬のバランス」が重要だと考えます。
例えば、普通の業務時間の中で完成する事が到底難しいプロジェクトだったとしても、
自分自身に任されていることにより、本人にとってはとてもやりがいを感じられたり、
プロジェクトを完遂したことにより給与のベースアップ・賞与の支給・昇格など
労働者に対する「インセンティブプラン」が用意されている事により、
労働者の納得感や欲求が満たされているかどうかと言う事です。
※ここの部分に関して、「業務時間の範囲で出来る仕事を受けてくるのが会社側や幹部の役目だろう」というご意見に対しては、否定も肯定も致しません。仕事をとってくる方も頑張ってとってきた仕事であることから、「一丸となってやり遂げよう」と考えるいわゆるブラック的な発想なのかもしれませんが、その点はご容赦ください。
高度成長期であれば、経済成長に合わせて仕事が増え、雇用も増え、増益し、給与も増える。
一昔前の過去であれば「人数×売上」または「業務量÷人数」と言う図式で企業が成り立っていました。
(ものすごい極端な図式で恐縮です。)
しかし、昨今では、高度成長期の図式が当てはまらないビジネスも多く出現していますし、
むしろ、当てはまらないビジネスが大多数なのではないでしょうか。
過去の経済環境と現在では、業態・ビジネスの仕組み・労働環境、
労働者の働き方や選択肢も大きく変わっている事が本質にあると考えています。
⇒続きを読む:ブラック企業と現代 <後編>/発信されるべき真実
[co1] [flow]Author Profile
Latest entries
- 2022.12.28炎上事例人気YouTuberのダメ出しに批判殺到
- 2022.12.27炎上事例自社商品を無断撮影し炎上
- 2022.12.26炎上事例元男性YouTuberの女湯レポに批判が相次ぐ
- 2022.12.16炎上事例踏切内に侵入する動画が拡散され炎上